中国の人気ドラマ 「続編」の製作はなぜ難しい? (2)
続編がオリジナルよりも劣る別のパターンには、製作者が自分自身に対する要求を下げてしまうことが関係する。ドラマは小説の創作とは異なる。小説は他人の力を借りずにすべて自分の手で完成できる作業だが、テレビドラマは数千数万の兵士を率いる軍隊のように、多くの人々と共同で作業を行い、しかもどこかの部分でミスが起きると、大きなトラブルへと発展する。ドラマがヒットすれば、脚本家、監督からカメラマン、録音師、美術、衣装、メイク係に至るまで、あらゆる人が栄誉を手にすることができ、共に同じ目標に向かって仕事をする過程は素晴らしい記憶となる。もしプロデューサーが続編を撮ることを決定すれば、制作チームが再び集結することも決して難しいことではない。問題は、その中の誰かが、自分1人でできないことはないと奢り高ぶる気持ちが出てくることだ。ある俳優は越権行為で脚本に手を加えさせたり、ある監督は脚本を待たずにクランクインしたり、ある会社は20話の素材を30話に水増ししたりする。製作チームが、評判や人気に頼ってやりたい放題になると、結果、作品の質が低下し、最後には視聴者が割りを食うことになる。最近放映されていた「青春期撞上更年期2」が途中で打ち切りになったのは、直接的原因は視聴率が低すぎるからだが、根本的な原因は脚本執筆や製作におけるさまざまな混乱が作品を退屈で生気がない、つじつまがあわない支離滅裂なものにさせたことによる。そして最後にはテレビ局と視聴者のどちらからも見放されたのだ。
また別のパターンとしては、脚本家に表現したいことがないわけでも、制作側が良い作品作りを放棄したわけでもなく、単に実力不足という場合もある。名作ドラマはすべて優秀な製作チームから生まれたもので、これらの作品を超えるには、やはり優秀な製作スタッフが必要となる。もし脚本家が優秀でなければ、続編を手掛けたとしても、自ら進んで恥をかくようなものである。また、たとえ続編の脚本家が優秀だったとしても、あらかじめテーマが与えられた枠の中で、原作の水準を保つことはやはり相当難しい。最も典型的な例だと、新シリーズのテレビドラマ「新編集部故事」が挙げられる。オリジナルドラマを手掛けた中国の人気作家・王朔(ワン・シュオ)と馮小剛(フォン・シャオガン)監督は、当時北京的なユーモアと脱構築の意識の下に、才気を発揮して、ドラマは圧倒的な人気を博した。その後多くの者がこのスタイルを後追いしようとして、色々と手を尽くしたが、上手く行かず、いずれも成功しなかった。新シリーズの製作チームが努力していないとは言えないが、いずれにしてもオリジナルとの落差を埋められずにいる。王朔は中国の一時代の話し言葉やスタイルさえ変えてしまったほどの優秀な小説家・脚本家だが、新シリーズは単にネットにあふれた断片的なエピソードを取り入れたり、社会現象や批判を追いかけているだけに過ぎない。断片的な情報にあふれた現代では、真の構成力だけが人の心を深く感動させることができる。
続編を撮影することはかくも難しい仕事にもかかわらず、なぜこんなにも多くの人が後を追うのか?それは、続編が簡単に稼げるビジネスだからだ。1作目の人気があれば、宣伝のことを心配する必要もなく、逆にマスコミは自主的に報道をしてくれる。また、放映についても心配は無用だ。テレビ局のバイヤーのほとんどが実績至上主義者だからだ。さらに、視聴率についても心配はいらない。マスコミが自主的に宣伝を行ってくれる上に、以前の視聴者たちも引き続き視聴してくれるので、ある一定以上の視聴率が保証されるからだ。しかしながら、創作という観点からすれば、続編はまるで落とし穴だ。しかも越えるのが非常に難しい大きな穴だ。オリジナルドラマのブランドを打ち出せば、視聴者の期待は否が応でも高まる。しかし、オリジナルと同じテーマで、単に制作チームが新たに変わっただけでは、人気を得るのは難しい。思い切り逆転させるには、想像力と才気が必要であり、難易度は極めて高い。人気ドラマのリメイクも同様であり、数だけは異様に多いが、ほとんどが評判を落としているのが実情だ。
しかし、これは続編は必ず質を保てないということを意味しているわけではない。米国の映画「ゴッドファーザー」パート2は、パート1の質を凌駕しているし、香港のテレビドラマ「◆心風暴」(◆さんずいへんに唐)の第2シリーズは非常に高い評価を受けた。このほかにも、中国中央テレビ(CCTV)が現在放映している「闖関東前伝」は放映開始からすでに新しい現象を起こしている。重要なのは本当に言いたいことがあるのか、それをちゃんと伝えようとしているか、ということだ。当然、視聴者は質の高い続編を見たいと思っているが、あらゆる続編がオリジナルを超えることを期待しているわけではない。まさしく、「努力を続ければおのずと成功するし、それで失敗しても後悔はしない」という言葉のとおりだ。(編集MZ)
「人民網日本語版」2013年6月6日







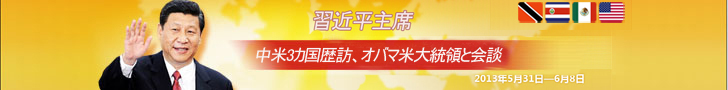




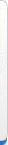
 関連記事
関連記事 英国 赤ちゃんのワイルドなヘアスタイル
英国 赤ちゃんのワイルドなヘアスタイル 年収100万元以上のバストモデル
年収100万元以上のバストモデル シンプルな粽子が今年のブーム
シンプルな粽子が今年のブーム 第9回中国(北京)国際園林博覧会
第9回中国(北京)国際園林博覧会



